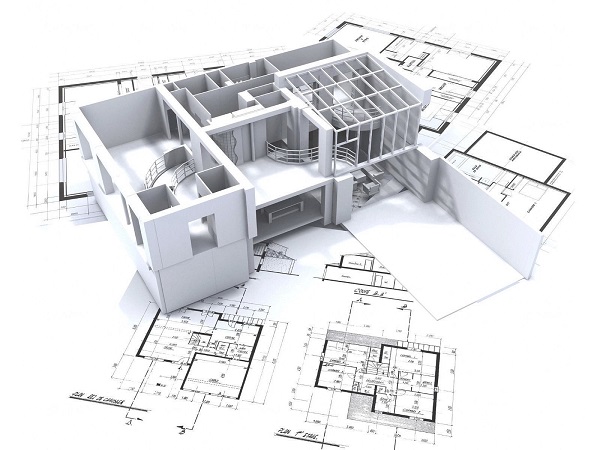大阪・関西万博 EXPO 2025 視察レポート
先日、私達は大阪・関西万博 EXPO 2025を2日間にわたり視察しました。建築コンサルティングとデザインを手掛ける私たちにとって、万博はまさにインスピレーションの宝庫でした。
各国が趣向を凝らしたパビリオンの外観デザインは、それぞれの国の文化や技術が凝縮された芸術作品そのもの。独創的なフォルムや素材の組み合わせに、思わずため息が漏れました。内部に足を踏み入れると、最先端の技術を駆使したディスプレイやインタラクティブな展示が広がり、まさに未来を体感するような驚きと感動の連続でした。
その上パビリオン以外の付属する建物や工作物にも、細部にわたるこだわりと高いデザイン性が感じられ、私たちが普段取り組んでいる建築デザインの奥深さを改めて実感しました。
また、今回は翻訳アプリを活用し、世界中から集まった多くの人々との交流も実現しました。異なる文化を持つ人々の話に耳を傾け、直接コミュニケーションを取ることで、デザインの背景にある思想や、それぞれの国の価値観に触れることができ、大変貴重な文化交流となりました。
今回の万博視察で得た多くの感動と学びを、今後の私たちの建築コンサルティングやデザイン業務に活かし、お客様により一層の価値を提供できるよう努めてまいります。

IT 事業、新たなフェーズへ

昨年2024年3月1日に発足いたしましたIT部門は、この1年で目覚ましい発展を遂げ、この度IT事業部として新たなフェーズへと進むことになりました。建築デザイン業界の枠を超え、デジタル技術の可能性を最大限に活かし、お客様の多様なニーズに応えるべく、IT事業部は以下のサービスを専門的に提供してまいります。
- 企業のIT経営管理に関する診断・助言・指導支援
- ソフトウェアやアプリの開発、ネットワーク環境の構築・整備
- 業務に最適なシステムの設計から開発、運用、保守までの一貫した対応
- IT人材の育成を目的とした、スキルや知識の習得を支援する各種サービス
IT部門を発足
この度、弊社では新たな一歩を踏み出し、新規のIT部門を発足いたしました。この部門の設立は、弊社の成長と未来に向けた戦略の一環として、重要な取り組みです。
建築デザイン業界は常に進化しており、デジタル技術の急速な進歩は私たちに新たなチャンスを提供しています。
このIT部門の設立により、建築デザインだけでなく、さまざまなお客さまのニーズに対応した価値あるサービスを提供していくことになるでしょう。
新規IT部門のメンバーとして、優れた技術力と情熱を持つチームが結集しています。
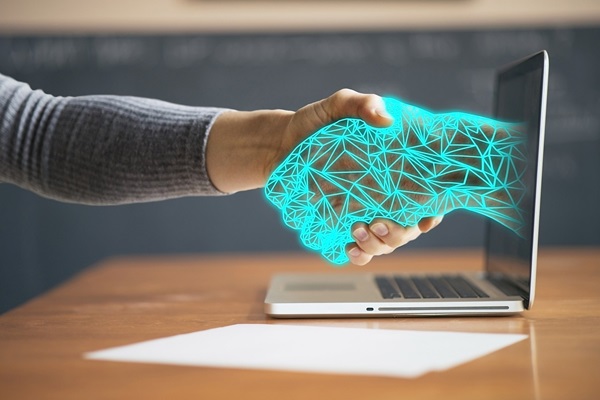
アイヌの人たちの家
アイヌは北海道、樺太、千島列島を主とし、現在は北海道に多く居住している先住民族の人々のことを指します。彼らは独自の歴史や文化を持っており、その歴史や住宅事情を学ぶ目的で、アイヌの人々の暮らしぶりを知ることのできる施設、「ウポポイ」を訪れました。

アイヌの人たちの家をアイヌ語で「チセ」といいます。骨組みの木や屋根・壁など家をつくる材料は、すべて自然のものを利用しました。たとえば、骨組みの木はハシドイやヤチダモ、壁や屋根の材料にはアシやササなどの草やキハダや樺といった木の皮などが使われていました。チセを建てるときは、材料を採ってきて家を建てるまでコタンの人たちが協力しあいました。チセは、屋根の傾きが4方向にあり、多くは入り口のところに玄関や物置として使われた小さな部屋がついていました。大きさは20㎡から100㎡程度まで、さまざまだったようです。
このチセの内側は四角形の一間で、真ん中よりやや入り口寄りに炉があり、窓は入り口から入って正面に1ケ所と右側(または左側)に1・2ヵ所ありました。このなかでも特に正面の窓は神様が出入りする窓といわれ、とても大切にされました。また、左奥には宝物置き場があって漆塗りの容器や刀などが飾られ、その上には家の神様が祀られていました。チセの中では、家族が座る場所やお客の席、寝る場所なども決まっていたようです。

サン・イグナシオ・ハイツ
サン・イグナシオ・ハイツは、アメリカアリゾナ州グリーンバレーにある55歳以上のコミュニティ(分譲地の総称)のことです。現地ではポピュラーなこの住宅開発の様子を視察してきました。
このコミュニティには、住宅所有者にさまざまなアメニティ(アメニティセンター、アウトドアレクリエーション、クラブやアクティビティ、屋外プール、ゴルフコース)と娯楽の機会を提供する非営利組織があります。
工法は建物の床、壁、天井をそれぞれ"面"で構成するところに特長があります。日本の在来木造が桁、梁、柱といった"軸"で構成するのとは、工法の発想が全く異なります。
海外の間取りで方位はあまり気にしないみたいですね。
日本の間取りでは、太陽光を取り入れることを考えて、リビングを南側に持ってきます。ですが欧米だと、玄関から入ってすぐ近くにリビングがあります。理由としては玄関の近くにリビングがあると、家族同士が顔を合わせやすいメリットがあり、家族とのコミュニケーションを大切にする考え方からのようです。平日は家族で一緒に過ごし、休日はゲストを招いてホームパーティを開くのにも都合が良いようです。
また日本と違い、玄関ドアは防犯のことを考えて内開きになっています。外開きの玄関ドアは、金物(丁番)が屋外にある為、これを壊せばたやすく室内に入ることが可能になるからです。

日本の伝統技術を訪ねて

福岡県大川市は日本有数の家具産地として知られ、家具の生産高日本一を誇る木工のまちです。良質な木材を使用し、伝統の技術はそのままに現代の日本家屋のスタイルに合わせて制作される家具は、デザイン性と技術の高さが高く評価されています。
今回は、このまちで受け継がれている畳・組子・家具等の伝統技術を見学させて頂き、たくさんのお話を伺うことがことが出来ました。このような伝統的な建築技術を初めて目の当たりにしたスタッフは、その繊細な作業にとても感銘を受けた様子で、「こういった技術をもっと自分の国の人にも是非知ってもらいたい。風俐プロジェクトを広げていきましょう。」と、興奮気味に語っていました。

国指定重要文化財 – 中村家住宅
日本各地で緊急事態宣言などの制限が解除された初秋、お客様との打合にて沖縄を訪れました。沖縄にはその地独特の建設様式があり、以前から訪れてみたいと思っていました。特に中村家住宅は、国指定重要文化財に指定されている、貴重な木造建築物です。
中村家住宅は琉球王朝時代に建てられた当時の上層農家の民家で、1956年に琉球政府により重要文化財に指定され、1972年に沖縄が変換されるのを機に国の重要文化財となりました。第二次世界大戦の沖縄戦を奇跡的に乗り越え、琉球王朝時代の暮らしを今に伝える貴重な歴史的建造物で、保存状態も良く家の内部も見学できます。
中村家住宅が建てられた琉球王朝時代は中国との貿易が盛んで、その影響から中国式を取り入れた建築物も多くありました。こうして日本式と中国式の利点を生かし、亜熱帯気候に合わせ守り神のシーサーが載っている赤瓦の屋根。
家屋の周りには琉球石灰岩の石垣があり、その内側には防風林の役目を果たすフクギが植えられています。
内部には、大きな仏壇や火の神様「ヒヌカン」等、日本本土とは違う文化を感じることができます。
当日は、建築を学んでいる琉球大学の学生もいて、学生同士で意見交換をしていました。

町屋巡り研修を行いました

現在進行中のプロジェクトメンバーで、京都で研修を行いました。京都の歴史が刻まれた町家は、古き良き日本文化の象徴であり、そこに宿泊することは外国人観光客にとって特別な価値のある体験となります。今回は、外国人にとっての日本家屋というのもがどういったものなのか、また日本人にとっての日本家屋との違いなどの観点から、地元の方にもお話を伺うことができました。メンバーの中には、町屋と呼ばれる昔の長屋のような日本家屋の宿泊施設を利用したことのない者もいて、真剣に話を聞いていました。京都の町屋文化や風習などについて教えていただいたり、日本家屋の利点などについて意見交換などを行いました。